
日本サッカー協会(JFA)の審判委員会は3月18日、レフェリーブリーフィングを開催。今2025シーズンのJリーグにおいて、激しいフィジカルコンタクトの場面でファウルを取らない場面が増えたことについて、プロフェッショナルレフェリーでもある扇谷健司審判委員長兼JFA理事は、こう強調した。
「我々としてはAPTを伸ばすために、何か判定基準を変えたというのは一つもございません。競技規則が何か変わったわけでは決してありません」
ここでは、ファウル基準についての扇谷氏のコメントから読み取れる、日本サッカー界の「事なかれ主義」について考察したい。
関連記事:JFA審判委員会が述べたレフェリング課題。乱れた接触プレーの判定標準【現地取材】
ファウル基準についての扇谷氏のコメント概要
扇谷氏はこう続けている。
「ただ、判定の標準は全体として上げていきたいと思っています。2050年までに日本代表がFIFAワールドカップを制するという目標があるなかで、これは我々審判員にとって新たなチャレンジとなっています。また、日本サッカーの象徴であるJリーグがより魅力的なものとなるよう、レフェリーサイドとして何ができるかを常に考えています」
「我々がレフェリーたちに伝えているのは、反則ではない事象に笛を吹くのはやめようということ。レフェリーたちはピッチ上でベストを尽くしてくれていますが、試合を映像で振り返ったときに、『この反則をとるの?』、『これは何の反則なの?』と疑問を抱く場面が少なからずありました。判定の標準を上げていくなかで、反則ではないプレーに笛を鳴らすのはやめようと。これに改めてトライしようと、レフェリーたちには伝えています」
「逆に言うと、反則にあたるプレーには笛を鳴らす。レフェリーが反則を確認したうえでプレーを続けさせるのであれば、アドバンテージが本来採用されるべきです」
「ただ、皆さんも試合をご覧になって分かる通り、本来反則と判定しなければならない事象に笛が吹かれなかった場面が、残念ながらあります。これに関しては、今シーズンからいきなりファウルの笛を吹かなくなったわけではなく、今までもあったと思うんです。先日もプロフェッショナルレフェリーのキャンプがあったなかで、反則にあたるプレーには笛を吹きましょう。プレーを続けさせるのであれば、アドバンテージのシグナルをしっかり示しましょう。そして反則でないものに笛を吹かない。その見極めをしっかりしましょうとレフェリーには伝えています」

額面通りに受け取れる?
この扇谷氏の発言を、Jリーグの選手や監督、そしてサポーターに至るまで、額面通りに受け取る人はどれだけいるだろうか。ましてや扇谷氏は現役審判員時代、数々の誤審でサポーターから不興を買っていた。
2023シーズンには既に審判委員長の任にあった同氏は、同年5月14日のJ1第13節鹿島アントラーズ対名古屋グランパス(国立競技場/2-0)で、鹿島のFW鈴木優磨がゴール後に木村博之主審を睨み付けたと一方的に決め付けたことがある。
その後のレフェリーブリーフィングで俎上に挙げ「非常に大きな問題。ああいうことがピッチ上で行われてはいけない。あれを相手選手やサポーターにやったら大乱闘になる。レフェリーがしっかり対応しないといけない」と、異例のコメントを発表。
これに対し鹿島は「レフェリーブリーフィングでは審判員の特定が避けられている中で、この件については選手名が特定された」と問題視し、委員会に抗議文を提出するまでに至っている。

責任の所在がうやむやに
今2025シーズンのJリーグはプレー強度を欧州並みに向上させることとAPTの増加を目指し、そのために明白なファウルが流されているという声がサポーターのみならず、実況アナからも疑問を呈する声が上がっていた。
審判委員会は今季のファウル基準について「ファウルには当然笛が吹かれるべき」と釈明したが、突然ともいえる基準の変更に付いては、選手からも不信感を抱かせ、ヴィッセル神戸FW大迫勇也も「大丈夫かJリーグ」とコメントするほどの事態に繋がっていた。
この混乱の背景として、審判委員会が「ノーファウルに笛を吹かない」という方針を強調されすぎたことで、現場の審判に過度なほどに「流す」ことを意識してしまったことが大きな要因であることは明白だろう。
JFAの意図は試合の流れを止めずAPTを増やすことだったのかも知れないが、実際にはファウルの基準が曖昧になってしまい、逆に選手の安全が損なわれる可能性が高まっただけという結果を招いている。扇谷委員長と同様に元プロフェッショナルレフェリーだった佐藤隆治審判マネジャーは具体的な事例を挙げて説明したが、これで誤解が解けたかと問われれば「否」と言わざるを得ない。
あまりにも納得させる材料に乏しいのだ。いっそのこと「今季からファウルの基準を緩和しました」と断言した方がよっぽど納得できると思われるが、そんなことをすれば批判の矛先は、宮本恒靖会長や野々村芳和Jリーグチェアマンに向かいかねない。責任の所在をうやむやにすることで、審判員のみならず“上役への忖度”も伺わせる。





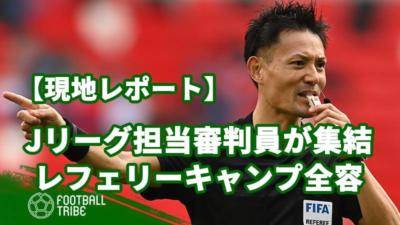
コメントランキング