
ブンデスリーガ第23節ボルフスブルク対バイエルン・ミュンヘンの一戦が17日に行われた。
試合は開始早々、ボルフスブルクが先制するもバイエルンが64分にドイツ代表FWザンドロ・バーグナーがクロスに頭で合わせ同点。さらに、試合収容間際PKを獲得。これをポーランド代表FWロベルト・レバンドフスキが危なげなく蹴り込み2-1で勝利を収め、バイエルンは公式戦13連勝を達成した。
ドイツ代表FWトーマス・ミュラーは後半62分から途中出場。同選手投入後、明らかにバイエルンのサッカーにリズムが生まれ始めた。その試合後、ミュラーは「僕らは自分たちのリズムをつかむことが出来なかった。ボールを持っていても攻撃的ではなかった。だから前半は0-1のスコアで折り返すことになったんだ」と前半の内容を分析。そして「後半開始と同時に僕らは攻撃で全く違った姿勢を見せ、多くのチャンスを掴めた」と振り返った。
最後に、見事逆転勝利を収めたチームに対して「このチームは最高だね」とチームへの愛情を表現した。
ミュラーはバイエルン一筋18年。トップチームでは2009年にデビュー。これまでにバイエルン通算422試合に出場し168ゴール141アシストを記録している。今季は公式戦27試合に出場7ゴール8アシストを記録し首位をひた走る同チームに欠かせない選手の一人だ。
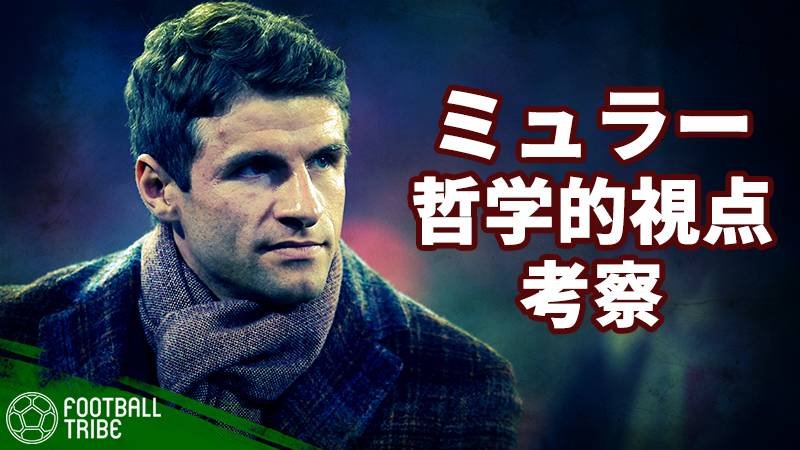
フットボール界のエニグマ、トーマス・ミュラーを哲学的視点から考察する
著者:Travis Timmons(BundesligaFanatic.com)
※エニグマ(enigma)とは、西洋語で「謎」、「なぞなぞ」、「パズル」等を意味する。

トーマス・ミュラーは、フットボールの世界で最も奇妙でミステリアスな選手かもしれない。私は2010年のワールドカップ以来彼に魅了されてきたが、他の人々と同じようにまだ彼のことが理解できていない。平凡でありながら卓越し、単純なのに人を欺く彼を説明するには新しい視点が必要になる。

ミュラーをエニグマとして認識することは、彼を語る上での第一歩だ。例えば『These Football Times』のカラム・ライス=コアテスは、ミュラーはペップ・グアルディオラ監督の下でのポゼッション・フットボールで、より楽観的でひより見的プレーを身につけたとしている。

また『theraumdeuter.com』はミュラーをアドルフォ・ペデルネラ、ヒデクチ・ナーンドル、アルフレッド・ディ・ステファノ、ミハエル・ラウドルップ、フランチェスコ・トッティ、アンドレア・ピルロ、そしてリオネル・メッシらと比較している。彼らに共通するのはフィールド上を動き周り、スペースを見つけ、自分のタイミングで相手を崩す自由を与えられていたことだ。ミュラーはキャリアの中で前線のすべてのポジション(左、中央、右)でプレーしてきた。

戦術的に見ると、ミュラーが右サイドで最良のパフォーマンスを見せることに最初に気付いたのはルイス・ファン・ハールだった。次にメッシとの関係をヒントに、グアルディオラがマークの集中するロベルト・レバンドフスキの空けたスペースへ(右サイドを始発点に)動き回る自由を与えた。これをきっかけにミュラーは躍動し、これまでで最高のシーズンを過ごしている。そしてカルロ・アンチェロッティとユップ・ハインケスの下では、主にこの役割を続けている。

実際に右サイドを起点にピッチ中を動き回るミュラーだが、それだけでは彼のポジショニングのすべてを説明することはできない。なぜならピッチ上の彼は幽霊のように、追いかけることが難しいからだ。私はミュラーの映像を90分ほど見て、動き、ゴール、アシスト、プレッシング、ドリブルなどのプレーリストを作っていった。この経験は彼のプレーを理解するうえで、大きな助けとなった。

まず気付いたのは、ミュラーが予想外のアングルで画面に飛び込んでくる事だった。多くは右サイドから、そして時には矢のように真っすぐ前線へ駆け上がってくる。まるでスペースが空く前にそれを予知しているかのようだった。どんな状況でも彼は何かを起こせる。彼はユーティリティープレーヤーではないが、その身長、力強さ、ドリブル、パス、バランス、決定力、そして両足の器用さを考えれば、彼ほどボールを持った時に頼りになる選手はいない。

しかしミュラーについて一番重要なのは、彼がまるでアルゴリズムによってあらかじめプランが決まっているかのようにプレーすることだ。それはロボットのように機械的にプレーしているという意味ではない。彼は他の選手よりも先に、プレーの展開を読めるのだ。私の考えでは、ミュラーはほとんどためらったり一時停止することがない。だからこそバイエルンで一番足が速いわけではない彼が、他の誰よりも速いスピードでプレーすることができる。そこには「試合を読む」という言葉だけでは的確に表現できない何かがある。

それは古代ギリシャ哲学で「実践的な知」を意味する「フロネシス」と言えるかもしれない。ミュラーは正しい事を、正しいやり方で、正しい時に、正しい場所で、正しい理由から実践している。「フロネシス」は彼を一言で表現するのに最も適した概念だ。他のエリート選手たちもある程度はこうした特性を持っていると言えるだろうが、「正しさ」という点でミュラーは飛び抜けている。
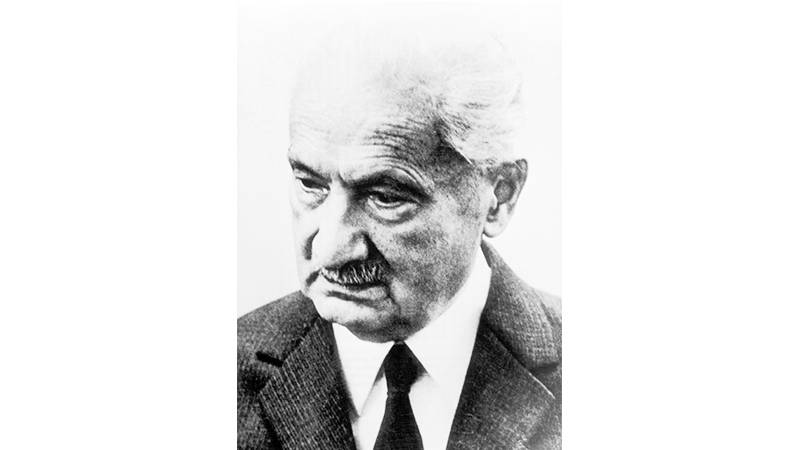
哲学者のマルティン・ハイデッガーは著書の『存在と時間』で、人間が単純に満たすことができる空っぽでニュートラルな入れ物としてのデカルト的な空間(スペース)認識を批判している。ハイデッガーは空間を単に現象学的に捉えた。重要なのは人間の体験を通じて、空間について考えることだ。

フットボールについて語る時、その空間認識はデカルトの定義に基づいている。選手は機械的にルールに従って動くことが求められる。しかしハイデッガーの基本的なポイントは、空間は「ケア・ストラクチャー」と呼べる重要性と可能性によって経験されるということだ。私たちは空間を「満たす」のではなく、常に世界に投げ込まれて可能性を考え、意味を探し、計画を作り、行動しているのだ。そして我々は過去または未来に基づいて、空間を経験する。つまり空間は常に私たちが過去に何をしたか、あるいは将来何をしようとするかで意味を持つことになる。

サッカーの試合は、これらのハイデッガーの概念を適用するのにぴったりだ。22人の選手がそれぞれの方向へ動く時、フィールドには様々な意味、重要性、可能性、動きが存在する。スポーツとしてのルールと100年以上の過去の経験と例は、私たちがサッカーを経験する「ルール」を形成している。もちろんこの既存の意味は選手を共通の期待、共通の動き、共通の可能性へと制限する。

また選手は主に過去のトレーニング、動画分析、あるいは過去のプレー経験に頼っている。それと同時に未来について考え、次の動きを探し、次に何が起こるかを過去の経験に基づいて予測する。言い換えれば、サッカー選手は過去に基づいてプレーし、同時に未来について考えているのだ。

現代のサッカー選手は、自動的な動きやパターンに従ってプレーするよう指示されている。私はそれを悪く言うつもりはない。むしろ避けることができないものだ。実際、ハイデッガーの論理によれば、ほとんどの選手は指示がなくても既存のプレーの仕方に従うことになる。幸運にも私たち観戦者にとってはこうした機械的動作は美しいもので、しばしば最高の選手やチームを象徴するものだ。トーマス・トゥヘルのボルシア・ドルトムントや、ユルゲン・クロップのゲーゲン・プレッシングがいい例だろう。

だからこそ、ミュラーは私たちを困惑させる。彼を経験、理解するための既存のフォーミュラがないからだ。ミュラーのユニークさを説明するには既存のフットボールの概念ではなく、哲学とハイデッガーの言葉の方がふさわしい。

おそらくミュラーは他の選手のように「過去」や「未来」に縛られていないのだろう。代わりにミュラーは「現在」の選手であり、他の選手とは違う空間の認識をしているのだ。それにより、ミュラーにとって空間は他の選手が認識するより多くの、あるいは別の可能性をもっている。

ミュラー自身も彼のプレーにはまずタイミング、次に空間が重要だと語っている。彼にとっては、時間の感覚がすべてだ。ペップ・グアルディオラの指導の下で大きく成長したのも不思議はない。スペイン人指揮官は、彼にユニークな役割を果たすための自由を与えていた。

深い意味で、ミュラーは一歩下がって試合を手元に手繰り寄せる。哲学者のハンス・ウルリッヒ・グンブレヒトは著書『Fascinations: In Praise of Athletic Beauty』で、こうした落ち着きについて語っている。重要なのはミュラーのような人間にとって、落ち着きは時の流れを遅くするということだ。私たちにはミュラーが他の選手より速く試合を読んでいるようにみえるが、私の考えでは彼は実際には試合を比較的ゆっくり経験している。これは他のトップレベルのアスリートが、時間がゆっくりに感じるのと似ている。

しかしそれだけではなぜ、またどうやってミュラーのような選手にそれが起きるのかまでは分からない。もしかしたら他により良い説明の方法があるのかもしれない。しかし今のところ私にとっては哲学、特にハイデッガーの現象学的なアプローチが、ミュラーを理解するうえで最も説得力のあるものだ。






コメントランキング