
模擬試合でのVARトレーニングも
海外サッカーの試合映像を用いたトレーニングのみならず、JFA夢フィールド内での模擬試合を通じたVAR研修も行われた。
同施設のグラウンドで行われる模擬試合をフィールドの審判員たちが捌き、VARやAVAR役の審判員が別室でこの試合の映像をチェック。実戦さながらの無線交信をしていた。
この日の夕方には、模擬試合でのVARチェックへのフィードバックや、審判員たちによるディスカッションが実施されている。今2024シーズンよりJFA審判マネジャーJリーグ担当統括に就任した、元国際審判員の佐藤隆治氏が本ディスカッションの司会を務めた。

伝わってきたVARの緊迫感
筆者にとって印象的だったのは、ペナルティエリア内における決定的な得点機会の阻止(Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity、通称DOGSO)で、ある主審が反則を犯した守備側チームの選手にレッドカードを提示した場面だ。
現行のサッカー競技規則ではDOGSOに該当する場面でも、反則地点がペナルティエリア内であり、その選手がボールにプレーしよう(正当にアプローチしよう)と試みたと判断できる状況では、レッドカードではなくイエローカードが提示されることになっている。これは相手にPKを与えたうえに一発退場、さらに次試合出場停止の三重罰を緩和するための規定だが、今回の模擬試合ではボールへのプレーを試みたはずの選手に、レッドカードが提示されていた。
審判員の名前は伏せるが、Jリーグの担当経験が豊富なこの主審、実は競技規則を失念したわけではなく、VAR役審判員のトレーニングの一環として、わざと判定ミスを犯している。VAR役審判員が、この明らかに間違った判定について主審にオンフィールド・レビュー(※)を進言できるか。この場面ではこれが試されていた。
最終的には正しい判定にたどり着いたものの、この模擬試合でVARを務めた審判員は緊張のあまり、的確な言葉を発せず。佐藤隆治氏も当該審判員をフォローしていた。
「VARやAVAR役は緊張したと思います。実際に、すごく緊張したと言っていました。(無線交信時の)声を聞いても分かります。(その模擬試合で主審を務めた、経験豊富な)〇〇さんがそんな間違いを犯すわけがないと(笑)。こうした前提で入るので、どうしたら良いのだろうとなる。でも、間違えることは(誰にでも)あるんです」
「最終的な判定は正しいです。(オンフィールド・レビューのために)主審も呼べています。判定の正確さという面では良い。じゃあどうしたらこの時間(判定にかかる時間)を速くできるか。VARやAVARがどんなサポートをすれば、何を改善すればオンフィールド・レビューまでの時間を短縮できるでしょうか」
(※)VARの提案をもとに、主審が自らリプレイ映像を見て最終の判定を下すこと。

佐藤氏の提案は
この佐藤氏の発問のもと、この日研修に参加した全審判員による活発なディスカッションが繰り広げられることに。「複数の映像を(同時に)何回も流してチェックするのではなく、ボールにプレーしたことがはっきりと分かる映像があったので、それを1画面にして流せば良いのでは」と、ある審判員が最適な映像選びについて語った後に、佐藤氏も主審に対するVARの進言のしかたについてこのように提案している。
「僕がこういうシーン(DOGSO)を見ていると、イエローカードにした理由は何ですか、レッドカードにした最大の理由は何ですか。こういう聞き方(をするVARが多い)。たとえば『ホールディング』(相手選手を掴む反則)と主審から言われれば、その反則をとっているのかと(主審の意図が)分かる。何の反則をとったのかを訊く。この言い方も(方法の)ひとつですよね」
判定の正確さと、VARレビューにかかる時間の短縮の二兎を、佐藤氏や各審判員は追っている。彼らがこなしている厳しい研修が、今2024シーズンのレフェリングに活かされるのを願うばかりだ。







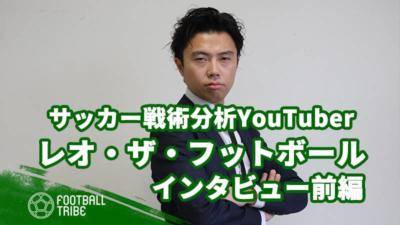
コメントランキング