
今2025シーズンのJリーグで、選手のみならず観客や視聴者を戸惑わせているファウル基準の曖昧さ。その元凶となっているのが、開幕直前の2月にJリーグチェアマン野々村芳和氏が打ち出した「APT(アクチュアルプレータイム)」の増加というものだ。
APTとは、試合時間90分+アディショナルタイムのうち、ボールが実際に動いている時間を指す。この数字がJリーグが欧州と比較して劣っていることを問題視した野々村氏が、“思い付き”のように「APTの増加」を打ち出し、現場の大混乱を招いた。
「国際競争力を高めるため」と強弁する野々村氏だが、果たしてそれは真実か。APTが増えることによって、Jリーグは魅力的なものとなるのか。欧州5大リーグと比較して検証したい。
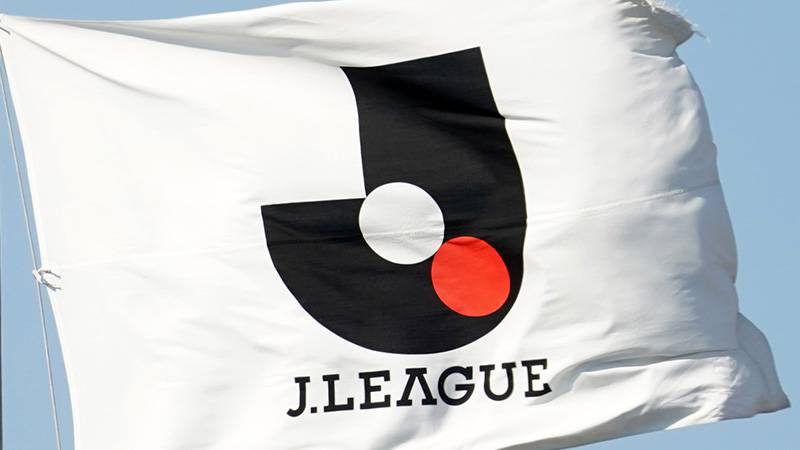
JリーグがAPTを重視する理由
JリーグがAPTを重視する理由には、ファウル、ボールアウト、選手の倒れ込みなどによる試合の中断を減らすことで、テンポの速いサッカーと質の向上を目指すことが挙げられる。Jリーグ公式サイトでも、トラッキングデータ(走行距離やスプリント回数)とともにAPTが取り上げられ、リーグ全体の哲学が反映されている。
Jリーグは発足当初から欧州サッカーをモデルとしてきたが、フィジカルやインテンシティーで差があるのは事実であり、APTを増やしたくらいでそこに追い付くのは一朝一夕では不可能だろう。しかしAPTを増やすことで、試合の密度を高め、選手の技術や戦術を磨く時間を確保しようとする意図もある。特に近年、ACL(AFCチャンピオンズリーグ)をはじめとする国際舞台での競争力強化が課題とされており、APTは改善点の1つとしての物差しとなっている。
また、Jリーグでは、審判員の能力を評価する1つの基準としてAPTが用いられることがある。笛を吹いたことによる中断が長いとAPTが減少し、逆に些細なボディーコンタクトでは笛を吹かずに流すことで、自ずとAPTが増える。当初は審判の質を高める取り組みと考えられていたが、逆に“流すことが正しい”という風潮となったことで、明らかなファウルまで見逃される結果を招き、選手から不興を買っている。

欧州5大リーグでのAPT注目度
一方で、欧州5大リーグ(プレミアリーグ、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、 リーグ・アン)ではAPTが注目されることは少ない。あくまで“マニアックな数字”として扱われている。
プレミアリーグはフィジカルコンタクトとオープン展開が特徴で、走行距離やスプリント回数、プレッシング強度などのデータが重視される。APTよりも、インテンシティーやゴール期待値が試合分析の中心だ。
ラ・リーガでは、テクニックとボール支配率、パス成功率が注目される。APTについても議論に上ることはあるものの、試合の質を測る指標ではない。
セリエAは、何と言っても監督同士の戦術的な駆け引きが最大の見どころで、守備の組織力やカウンターの精度が焦点で、戦術の完成度が優先される傾向にある。
ブンデスリーガは、ハイプレスとトランジション(攻守の切り替え)が重要視され、走行距離やスプリント数のデータが先に立つ。APTは時折、話題に上るものの、試合の魅力を測る指標とは見なされていない。
リーグ・アンは、アフリカ系選手が多いのが関係しており、個人能力とスピードが強調され、ドリブル成功数やシュート数が注目される。APTは議論にも上らない。







ダイナミックプライシング導入の浦和ホームゲーム。高額チケットにG大阪サポ等不満
文: Shota | 2025/3/23 | 19
久保建英の他に伊東純也との同時起用でも問題?堂安律のプレーが話題
文: Shota | 2025/3/25 | 16
セレッソ大阪vsFC東京で…山本雄大主審と山下良美VAR担当に批判相次ぐ
文: Shota | 2025/4/21 | 15
京都サンガvs柏レイソルでハンド認められず…清水勇人主審やVAR担当に異論も
文: Shota | 2025/4/2 | 15
京都エリアスが帰化・日本代表入り熱望!Jリーグの特徴は「ブラジルより…」
文: Shota | 2025/4/13 | 14